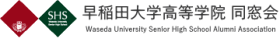【OBの活躍】「地域鉄道の再生と物流の改革に挑戦する」33期 山田和昭
1982年(昭和57)卒 33期 山田和昭 K組 理工
地域鉄道の再生と物流の改革に挑戦する
1982年卒業 K組 ドイツ語の山田 和昭です。松村健太郎さんよりお声がけいただき、寄稿いたします。今は合同会社日本鉄道マーケティング(https://jrmkt.com)と名付けた会社で地域鉄道の再生や物流の改革など「移動」をテーマに仕事をしています。生きていくには必ず移動は伴うのですが、空気のごとく意識されません。しかし空気と同様に無くなったら困るのが移動なのです。
最近、地域鉄道の問題がマスコミを賑わせています。人口が減少し需要が減り赤字が増えて維持が難しくなっているという論調が大半です。しかし、これが全て間違いで、本当の原因は地域鉄道が図書館や消防署のような公益事業なのに、公益性は無視され独立採算で「赤字」とされ、投資不足から時代遅れになり、クルマにシェアを奪われ、どうにもならなくなりコスト削減のため減便や値上げをした結果、通勤通学しづらい地域となり人流商流が萎み地域が寂れ地域経済も人口も縮小しているというカラクリです。前提や捉え方が違っているので政策が効果を出さず、地域と地域鉄道が衰え続けている惨状を見ていられなくなり、「もっとできる事があるだろう」と、12年前にIT業界を抜けて鉄道業界に飛び込みました。
■学院の鉄研が背景に
その背景は学院時代の鉄道研究部(鉄研)にありました。鉄研の合宿は現地集合現地解散で、それぞれが好きな経路で撮影・乗り鉄・乗車券収集などを楽しみます。学院の休みは長く長期の旅行もしやすかったのです。最初は山陰、そして九州、東北、北海道、信州、南紀などを巡りました。当時の国鉄は広域乗り放題の周遊券があり、多数走っていた夜行座席急行列車を宿代わりに、全国の鉄道を乗り回りました。国鉄改革でローカル線の廃止が発表され、「廃線になる前に乗っておかねば」と熱が入りました。乗ってみると通学生で混み合う路線が廃止になったり、炭鉱が無くなり使命をとっくに終えたような路線が動いていたりと、鉄道の経営面に興味を持つようになりました。全くの趣味でしたが、これが後に役立ちます。学院・大学と日本中を巡り終えた頃、国鉄はJRになりました。私は第一次AIブームの中IT業界に就職し25年にわたり販売・マーケティングに携わりました。Microsoftの寡占、インターネット、オープンソース、ビッグデータと著しい変化があり刺激的な毎日でした。
■ゼロからの鉄道業界
さて、IT業界を抜け鉄道業界に入るにも人脈も無いので鉄道関係のイベント・研究会に手当たり次第に顔を出し、先生方と知り合いになり仲間も増えていきました。稲門鉄道研究会のご縁で秋田の由利高原鉄道を紹介いただき、失業手当をもらいながら春田社長から地域鉄道経営を学びつつIT業界のマーケティングを地域鉄道に適用しようと、ネット/媒体広報や応援団設立などさまざまな活性化策を試し国交省日本鉄道賞では最終選考にまで残りました。その後、鳥取県にある若桜鉄道が社長を公募し、倍率30倍の中採用となりました。東京から鳥取へ夜行列車で旅立つ日、週刊プレイボーイの島地元編集長のバー「SALON de SHIMAJI」にお別れを告げに行った時、松村さんとお会いしたのでした。
若桜町は国勢調査の度に人口が15%も減る有様で、過疎を止めなければ地域も鉄道も持続できません。過疎の原因は林業などの産業喪失、不便な公共交通と鳥取市への転出でした。そこで鉄道を資源とした観光化と雇用創出、通勤通学の利便性を上げ鳥取市への転出を防ぐ2つの策を平行して進めました。鳥取稲門会を通じ、ロータリークラブやライオンズクラブなど地元資本の皆様からも応援いただき、2015年のSL走行社会実験は県・町など行政と鉄道事業者・沿線団体など28組織・380名ものボランティアにより開催され、人口1万8千人の地に集客1万3千人、経済波及効果1日1,800万円、広告換算効果4,745万円、鉄道を軸に県と2町が一体となる沿線の歴史初の事態となりました。廃止も検討された若桜鉄道がこのようなチカラを持っていることが実証され、地方創生総合戦略で地域の観光軸と位置付けられ、公費が投入され観光車両が導入され、便数も5割増え通学も便利になりました。

2015年に運行された「鳥取県発地方創生号」で、石破茂地方創生相(当時・右端)と並ぶ筆者(右から2人目)
その後、両備グループの空港アクセス航路 津エアポートライン(三重県)の責任者を経て、滋賀県の近江鉄道では住民連携体制を作りました。関西初の鉄道無料デイで鉄道に関心の薄い住民の関心を引き寄せ、昨年4月に公設民営方式に移行できました。ここでも稲門のご縁に助けられました。
現在は東京に戻り、福島大の吉田樹先生とYouTube教材「地域交通リ・デザイン」(https://jrmkt.com/elearning/)を作り、名古屋大の加藤博和先生「公共交通マーケティング研究会」(https://trans-market.jimdofree.com/)、関西大学宇都宮浄人先生「やさしい交通しが」交通まちづくり市民活動 (https://yasashiikotsushiga.wixsite.com/machizukuri)、早大レギュラトリーサイエンス研究所梅津先生「Rail-DiMec(鉄道の災害医療への活用)研究会」などのお手伝いをしています。

福島大の吉田樹先生と取り組むYouTube教材「地域交通リ・デザイン」
■大問題を抱える物流を改革したい
一昨年夏、米国を旅行し国内専用の53feetコンテナと20/40feet国際コンテナが鉄道で一体的に大量輸送されている姿を見てショックを受けました。日本の物流はトラック事業者のダンピングで低廉に抑えられていましたが、欧米が鉄道や艀で集約輸送するのに対し労働生産性は低く人手不足も招いています。国際幹線コンテナ航路で世界最大の北米航路は上海・釜山から津軽海峡を通り北米に向かいます。日本の港は貨物が少なく遠回りになるので幹線が寄港せず、日本を発着するコンテナの大半は釜山で中継されています。こういった物流の非効率が日本の競争力を下げているようなのです。そこで、国際コンテナ輸送を規範としたユニットロード化・標準化・システム化、港湾の集約化により国内物流の効率化と日本の競争力強化が図れないものか、早大の大森先生らにご相談しつつ模索をし、鉄道業界に入った時と同様に研究会や学会などに顔を出しています。会社のwebでは物流学会での講演録画も公開し、乗りものニュースにも記事を書いています。ぜひ皆様のお知恵をお貸しいただけましたら幸いです。
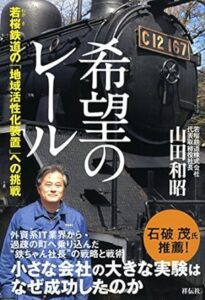
若桜鉄道での奮闘を綴った著書『希望のレール』(祥伝社)