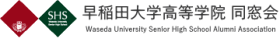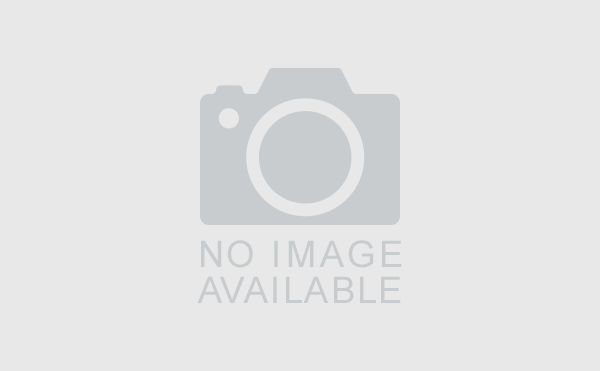【OBの活躍】 「ホルンを吹き続けて57年」 25期 辻村憲治
1974(昭和49)卒 25期 辻村憲治 F組 経済
ホルンを吹き続けて57年
今年5月に古希を迎える私が唯一続けている趣味、それはフレンチホルンの吹奏です。中学1年生で吹き始め、現在、高田馬場管絃楽団、早稲田の杜金管合奏団、ちばマスターズオーケストラという3つの団体に所属しています。年々技量が低下していて「いつまで吹いていられるのだろう?」と不安になることもありますが、大学時代の先輩の声掛けにより所属団体以外のオーケストラにも賛助出演するなど、この歳になって演奏機会は増えています。
昨年は4月中旬に都民交響楽団の演奏会に賛助出演しブルックナーの交響曲第7番でワーグナーチューバを担当したほか、5月下旬から6月上旬にかけてマウントあさま管絃楽団の一員としてオーストリアのウィーンとリンツへの演奏旅行に参加してきました。ウィーンでは楽友協会大ホール「黄金の間」でベートヴェンの「荘厳ミサ曲」を、リンツではブルックナーのお墓があるザンクトフローリアン修道院で「荘厳ミサ曲」とブルックナーの交響曲第7番を演奏しました。ウィーン・フィルが本拠地としている歴史あるホールとブルックナーが眠る修道院での演奏は生涯忘れ得ぬ想い出となり、新たな音楽仲間との出会いは今後の活動への大きな糧となりました。参加して本当に良かったと思っています。

ウィーン楽友協会 大ホールにて「ホルン後列中央が筆者」

ザンクトフローリアン修道院 祭壇前にて「ホルン&チューバ奏者」

ザンクトフローリアン修道院 祭壇裏にて「筆者とワーグナーチューバ(レヒナー製F管)」
11月上旬には早稲田の杜金管合奏団(ワセキン)の東北演奏旅行で宮城県気仙沼市と岩手県大船渡市、奥州市へ。ワセキンは東日本大震災からの復興を願って2011年の11月から隔年で現地での演奏会を開催していて、大船渡市、奥州市は7回目の訪問となりました。回を重ねるごとに聴衆の皆さんの表情も明るくなり、復興が着実に進んでいることも毎回実感できるので、今後も継続できればいいなと考えています。
そして、11月下旬には北海道の鶴居村で開催された「タンチョウの里鶴居村音楽祭」のスペシャルオーケストラに参加してきました。前日にタンチョウの探索と釧路湿原散策を行い、リハーサルを経て翌日の本番に臨んだのですが、人口2,430人の村で聴衆が400人以上集まり、まさに村をあげての「大音楽祭」であることが分かりました。この音楽祭は今年も開催される予定で、ワセキンも出演することになりました。再訪を楽しみにしています。

鶴居村音楽祭にて「左が筆者、右は指揮者石川征太郎氏」
原点は学院
長年演奏活動を続けている理由は、音楽を奏でることが好きだからということに尽きますが、なぜそれほどまでに好きになってしまったかというと、その原点は学院での部活にあります。
1969年3月21日、当時中学1年生だった私は杉並公会堂へ学院ウィンドアンサンブル(吹奏楽部)の第10回定期演奏会を聴きに行きました。プログラムはリムスキー・コルサコフの「シェヘラザード」、ガーシュインの「パリのアメリカ人」や映画音楽等のアレンジもので、中学校の吹奏楽部でコンクールの課題曲やマーチばかり吹いていた私にとっては実に新鮮なプログラムでした。そして、流れてくるサウンドは大人びていて、クラシック系の曲では時としてオーケストラのような響きが、ポピュラー系の曲ではお洒落な匂いがするのです。すっかり魅了されてしまった私は「学院に入学しウィンドアンサンブルに入部するしかない。」と決めつけ、3年後には入部を果たします。部員として活動を始めてみるとさすがは学院の部活、とにかく自由で楽しいのです。テレビ番組「吹奏楽の旅」で全国レベルの強豪校が一糸乱れぬ精緻な演奏を目指してスパルタ的な練習を重ねる様子が紹介されていますが、そのような練習とは無縁。指導者の大蔵康義先生は藝大卒のトランぺッターで、本物の音楽を追求しつつも部員の自主性を重んじてくれて、細かいミスをいちいち指摘するようなことはありませんでした。東京都の吹奏楽コンクールでは毎回銀賞でしたが、3年間の活動を通して音楽の楽しみを知りホルンという楽器の奥深さにも魅了され、年齢を重ねても吹き続けたいと思うようになっていたのでした。
学院を卒業して大学に上がると、迷うことなく早稲田大学交響楽団(ワセオケ)に入団。4年間ホルン漬けの生活を送り数々の大曲に挑みましたが、ショスタコーヴィチ追悼演奏会として1975年(2年時)12月5日と7日に演奏した交響曲第13番「バービィ・ヤール」は日本初演だったこともあり、特に感慨深い演奏会でした。また、毎年関東の大学オケの選抜メンバーで編成される「ジュネス・ミュジカル・シンフォニー・オーケストラ」に2年時から3年連続で参加したことも大きな経験でした。3年時の演奏会では、巨匠オトマール・スイートナー氏がブラームスの交響曲第1番を指揮することになり、初めてオーディションが行われました。N響の先生たちが25人ほどの候補者の中から4人のホルン奏者を選ぶという厳しい競争が待ち受けていましたが、幸いにも私は2番ホルン奏者として合格し、オトマール・スイートナー氏の圧倒的な音楽感に触れることができました。これは私の音楽感形成に大きな影響を与えた貴重な体験でした。この年(1976年)、ワセオケはカラヤン財団の招聘によりベルリンで開催されるカラヤンコンクールに出演することが決まっていたものの、諸事情により1978年に延期せざるを得なくなりました。インスペクターとして準備を統括していた私は団員への説明や事後処理で大変辛い思いをしましたが、1978年のコンクールで後輩たちが見事に優勝を勝ち取ったという報告を受け、苦労が報われたと感じたことを覚えています。ワセオケは現在も数年ごとに欧州ツアーを実施していますので、その礎を築くことに若干関与できたのではないかと思っています。
このように学院・大学時代に培った音楽への情熱は社会人になっても衰えることはなく、いくつかのアマチュアオーケストラに籍を置いて活動を続けてきました。そして、退職後はいつでも練習できる環境を活かし、冒頭で紹介したように活動の幅を広げています。この先何年続けられるかわかりませんが、ワセキンで活動を継続しておられる学院の4年上(21期)の先輩、川俣さん、山瀬さんを見習って頑張り続けたいと思います。