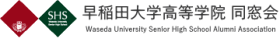【今思うこと】 「海洋国家日本を憂う」 13期 大山高明
1961(昭和37年)卒 13期 大山高明
「海洋国家日本を憂う」
学院を卒業してほぼ60年、正に「光陰矢の如し」であります。学び舎上石神井の記憶も薄れる中、とある縁で同窓会の山口真一副理事長より依頼を受けて本稿を認めております。 山口氏をはじめ2019年3月にメルマガを創刊された関係者の皆様には「学院のご縁」を大切にされる心意気に敬意を表させていただきます。小生、大昔は「都の西北」を聞くだけでジーンと胸がつまったものですが、やはりここ10年で感度が薄れました。でも早稲田は「人生大学」だと思い、慶応は無論、東大、明治、拓大だろうが早稲田の仲間だと考えております。

前列右端が筆者
さて、先ず小生の経歴を知っていただいた方が話の筋が想像できると思いますので簡単に記しておきます。
学院の自由な気風の中、当時創部されたアメリカンフットボールクラブに参加したものの仲間は10人足らずで試合の度にラグビー部から応援を頼んでいた有様でした。当時は正則高校が強かったように記憶しています。
早慶戦はありましたが、他にアメフトをやる学校は少なく、横浜の米軍基地ハイスクールに行って練習試合をしました。そこで古い道具を譲ってもらったり、当時珍しいハンバーグなどを食べた思い出があります。今や同クラブは全国大会の優勝候補にもなっており隔世の感があります。
また、まだ海外渡航が制限されていた三年の夏休みには団袋一つを肩に船でシンガポールに渡りマレー半島、タイ、カンボジア、ベトナムを汽車、相乗りバスなどで走破したのは当時高校生としては珍しいことであったようです。大学ではアメリカ遊学と南米大陸漫遊のため二年間休学、復学後は同好会少林寺拳法クラブに所属、卒業後OB会長を長年勤め、その間43番目の正式な部として体育局に認可されたことは極めて栄誉なことでした。就職は某航空会社にすべりこみ、ローマ、ニューヨーク支店の経験をさせてもらったものの、社風が肌に合わない等幾つかの理由が重なり20数年後に退社、父の創業した「日本海事新聞社」に転任、現在に至っております。
 「日本海事新聞社」は海運、海事業界の全国日刊紙で、読者は広く商社・金融にも及んでいます。皆様もご承知の通り日本は四面を海に囲まれた海洋国家です。日本の陸地面積は38万平方キロであり世界の中でも60番目に位置する資源小国ですが、大小6800もの島々を擁し、その海岸線はイギリスの2.3倍、中国の2倍、アメリカの1.5倍にもなります。それ故に海岸から200海里の経済的排他水域(当事国の主権を主張できる範囲)を含むとその総面積は陸地の12倍となり、陸と海を合わせると世界9位の広さを有する国となります。その広大なる海洋には水産資源をはじめとして「燃える氷」と言われる100年分のメタンハイドレートや様々な鉱物資源が大量に眠っていると推測されています。そのような海洋資源もさることながら、日本は第二次世界大戦の敗戦後、造船をはじめとした海事産業を基盤とした貿易等により経済大国への道を辿ってきました。現在でも石油をはじめとする消費財の9割以上は船舶による輸入に依存しております。更に日本は海洋という自然の防波堤により他国の侵入を容易にさせない、という地政学的に大きなメリットを受けています。このような「海の恩恵」を国民に広く知らしめるため平成8年に全国2261の地方自治体議会の承認、衆参両院約300名近い超党派議員の賛同及び全国138万人の街頭署名を得て、「7月20日海の日」が国民の祝日として制定されたわけです。しかし平成15年の「祝日三連休化法案」により「海の日」は毎年第三月曜日に移行させられることになり、単に「三連休」というレジャーを支える日になってしまいました。日本海事新聞社では「7月20日海の日」を国
「日本海事新聞社」は海運、海事業界の全国日刊紙で、読者は広く商社・金融にも及んでいます。皆様もご承知の通り日本は四面を海に囲まれた海洋国家です。日本の陸地面積は38万平方キロであり世界の中でも60番目に位置する資源小国ですが、大小6800もの島々を擁し、その海岸線はイギリスの2.3倍、中国の2倍、アメリカの1.5倍にもなります。それ故に海岸から200海里の経済的排他水域(当事国の主権を主張できる範囲)を含むとその総面積は陸地の12倍となり、陸と海を合わせると世界9位の広さを有する国となります。その広大なる海洋には水産資源をはじめとして「燃える氷」と言われる100年分のメタンハイドレートや様々な鉱物資源が大量に眠っていると推測されています。そのような海洋資源もさることながら、日本は第二次世界大戦の敗戦後、造船をはじめとした海事産業を基盤とした貿易等により経済大国への道を辿ってきました。現在でも石油をはじめとする消費財の9割以上は船舶による輸入に依存しております。更に日本は海洋という自然の防波堤により他国の侵入を容易にさせない、という地政学的に大きなメリットを受けています。このような「海の恩恵」を国民に広く知らしめるため平成8年に全国2261の地方自治体議会の承認、衆参両院約300名近い超党派議員の賛同及び全国138万人の街頭署名を得て、「7月20日海の日」が国民の祝日として制定されたわけです。しかし平成15年の「祝日三連休化法案」により「海の日」は毎年第三月曜日に移行させられることになり、単に「三連休」というレジャーを支える日になってしまいました。日本海事新聞社では「7月20日海の日」を国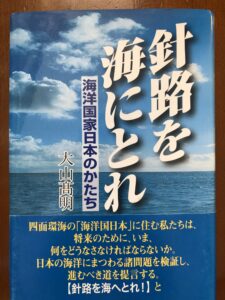 民の休日として再度固定化して、国民の皆さんが等しく海に関心を持っていただける日とするために静かな運動を展開しております。更に日本の商船隊は約2千500隻ですが、これに日本人船員約2500人を含めフイリッピン、インドネシア等の船員が約5万6000人乗船しております。海外から輸入された物資を各地方に運ぶ国内の貨物船は約5千200隻、日本人船員が2万8000人乗船しています。我々の生活基盤を支えてくれている船員達が世界に蔓延したコロナウイルス感染の危機にさらされたことも事実です。
民の休日として再度固定化して、国民の皆さんが等しく海に関心を持っていただける日とするために静かな運動を展開しております。更に日本の商船隊は約2千500隻ですが、これに日本人船員約2500人を含めフイリッピン、インドネシア等の船員が約5万6000人乗船しております。海外から輸入された物資を各地方に運ぶ国内の貨物船は約5千200隻、日本人船員が2万8000人乗船しています。我々の生活基盤を支えてくれている船員達が世界に蔓延したコロナウイルス感染の危機にさらされたことも事実です。
皆様すでにご高承の如く日本は国内外に様々な問題を抱えておりますが、「海洋国家日本」を軸にコロナ禍後の社会をどのように再生してゆくのか-―――ひとり憂えております。同窓の皆様からの何等かのご助言、ご意見などいただければ幸いです。
さて、最後になりますが当メルマガ創刊号で「我が人生」を語られたジャズ・トランペッターの外山喜雄氏は学院の同級生で最近ひょんな縁から60年近くぶりに交友が始まりました。「銃に変えて楽器を」という世界平和への壮大な夢に挑戦している氏と共に、もうひと踏ん張りしなければと自らを鼓舞するこの頃です。