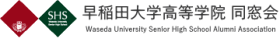【思い出】 「バラックの学院で薫陶を得た先生方」 5期理事 佐々木誠吾
1954(昭29)卒 5期 佐々木誠吾 G組 経済
バラックの学院で薫陶を得た先生方
周知の孔子の教えの一つ学而には「我十五にして学に志し、三十にして立つ」とある。その十五にして僕は希望の母校の高等学院に入学した。昭和二十六年三月の春、意気揚々として早稲田中学から高等学院の校内をくぐった。戦後六年、東京には空襲で負った焼け野原が多く散在し、生活と勉学は戦後のどさくさ時代である。生まれ育った浅草は丸焼けである。

昭25(1950)頃の旧戸山校舎
学院の校舎は広い大学のキャンパスにあった。穴八幡の前、石柱の立つ校門を過ぎると一周400 メートルのトラックの運動場が右手に出来て、そこを通過してゆるやかな坂を登った奥に我が学園はあった。右手に古材で建てた木造平屋建てが縦に長く並べた二棟、これが校舎である。それを繋ぐ渡り廊下の木造平屋建てのバラック、僅かなスペースだが、これが職員室である。奥に初代院長の竹野長次先生が温厚な眼差しで鎮座、三つ組みの背広をいつも着ていらした。隣りに事務主任の時岡孝行先生が端正に紳士然と仕えダブルの背広を着ていらした。校舎の造作はバラックの掘っ立て小屋だが、壊れた窓を風が素通していっても、お二人には風格があり威厳があった。竹野院長はのちに文学部長に、名誉教授に、時岡先生はのちに大学の就職部長、兼、理事に就き学園に尽くされた。
敗戦後のことゆえ、新制高等学続として発足した学院も、艱難辛苦の中に在った。竹野院長は学問と教育の健全な復活をめざし、時岡先生は学院の財政と経営に奮闘する臼々であった。お二方が机を並べていたことも、即ち両輪の健全、且つ円滑な運営の稼働を目指したものに他ならない。
長老で錚々たる先生方
クラスの担任を務めドイツ語担当であり西洋哲学者の川原栄峰先生は大学では助教授、初日、教室に入って教壇に立つなり黒板にドイツ語で「われ思う故に我あり」という言葉を流れるように書いた。学徒は深遠な命題を突き付けられた。これが最初のドイツ語の学習であった。学院での教育、学問、研究の神髄を物語って、学徒の自覚を促されていた。教室から見た壊れたガラス窓に、隣地の女子学習院の敷地の深々とした森が目に入ってきた。澄み切った視界が、心を浄めてくれた。
先生方の多くは大学から出講して来られた。長老で錚々たる先生方がいらした。文芸評論家の浅見渕先生、歌人の都筑省吾先生は文学論、樫山欽四郎先生は哲学、物理の篠崎、数学の清水、地学の大杉、東洋史の小林、原田、中堅の英語の遠藤、本間、内山、文学の石丸、三浦と云った先生方は今でも懐かしく思い出される。著名な樫山先生の哲学の授業には二人の生徒しかいなかった。先生の著書の「哲学序説」を教材とした。人間の存在と意識に追っていく講義で授業は難解であったが、感動的なものだった。第二語学にドイツ語を選択した僕は、三年生の時にドイツ語部の幹事長を務め部員の募集に新入生のクラスを駆け巡った。結果それまで四、五人だった部員がこの時は百名近くに膨らんで部活動が盛んになった。放課後の自主学習ではマルクスの共産党宣言の原書を読んだりした。文化祭は学生諸君の学習の自主性と創造性を求めた成果を発表する場でもある。その時、小冊子を発行して自ら執筆した。青臭い話だが、ヘッセと実存哲学を論じた。実存哲学に触れたわけは、川原先生と樫山先生に影響されたところが大であった。企画した小冊子に寄稿してくださった先生方は、当時の舟木文学部長、川原栄峰助教授、藤田赤二講師、高木実教諭の先生方であった。
ドイツ語読本で、高木先生のシュトルムのインメンゼーは陰影のこもった純愛小説だった。ドイツ語部の部長は藤田赤二先生だった。衣服も表情も仕草もダンディーだった。物静かで黒いベレー帽が良く似合っていた。早稲田へ向かって文学部の前当りに瀟洒なモンシェリと云う喫茶店があった。コーヒーを飲みに良く連れて行って下さった。先生に頼まれて御子息の家庭教師をしたことがある。奥さんが美しい人であった。たびたび夕食をご馳走になったりして学習は楽しかった。
夜行列車で向かった修学旅行
学院の行事の一つに学年別の修学旅行があった。一年の時に仙台松島と平泉の二泊三日の旅行があった。上野駅から夜行列車で向かったが車中、文庫本の佐藤春夫詩集を読んでいたら、担任の川原先生が「僕にも読ませてくれないか」と云われた。
二年生の時には新潟経由で佐渡旅行が行われた。連絡船で佐渡の両津港に着き、佐渡を横断する観光だった。相川でおけさ踊りを楽しみ、名勝の尖閣湾を観光した。パスの席では浅見先生と一緒だった。崖っぷちの狭い道路を行くパスにひやひやしていたが、浅見先生のその時の旅行記が後日NHKの深夜放送で朗読されていた。矢張り「ひやひやしながら」と書いていらした。
三年の時は北海道旅行であった。長旅だが夜行列車で青森まで行き、青函連絡船で津軽海峡を渡って行った。函館、湯の川から大沼公園の駒が岳を望みながら札幌へ、そして登別、洞爺湖へと行く。道南地方の七泊の豪華な修学旅行であった。殺伐とした時代、修学旅行は謂わば地方巡業、そしてまた芭蕉の「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり」と、時に人生の指針を暗示するに充分であった。その時に詠んだ小生の和歌について浅見先生が万葉調の調べがあって読みごたえがあると評してくださった。嬉しかった。
締めとして。打って出た社会の道はそれぞれだが、学院で薫陶を得た先生方、特に遠藤、大内、植田先生とは不遜ながら学び舎から生涯、肝胆相照らし互いに精進に励むなかであった。思い出は枚挙にいとまがないが、学院時代の学習生活は今でも鮮明に情熱的に僕の胸の内に生き続けている。
翻って今年、学院は意義深く創立七十周年を迎えている。杜甫の詩一節、古希である。又、七十にして矩をこえず、盤石の基盤に立って、精鋭の学徒諸君には常に早稲田精神を謳歌しつつ清新の気概溌刺として、チャレンジ精神を発揮して世にのぞんでもらいたいと念願している。

上石神井移転時の写真