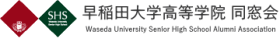【思い出】「青春そのものの濃密な時間」30期 西川均 (十一世 西川扇藏)
1979(昭和54)年卒 30期 西川均 C組 一文
「青春そのものの濃密な時間」
日本舞踊五大流派の一つであり、江戸中期以来300年を超える歴史を持つ西川流。十一世 西川扇藏こと西川均さんは、日本最古と言われる流派の伝統を受け継ぎ、様々な舞台で活躍されています。そんな西川さんに、学院・大学時代の思い出や芸事との関わりについて伺いました。
――まずは、学院入学のきっかけについて教えてください。
実は、当初の志望は学院ではなかったんです。高校受験の当時、既に舞台活動をしていたので、また受験をするのは嫌だなという思いはありました。ただ、行きたかったのは慶應で、学院は受験しませんでした。ところが日吉も志木も落ちてしまい、結局は渋谷の國學院高校に進むことになりました。それで土曜日に授業を受けていると、隣の神宮球場の周りで午前中から早慶戦の応援の練習をしている。その声が聞こえると、やはり悔しさが込み上げてくるわけです。しかし、当時慶應は再受験生を受け付けておらず、一方の学院は1浪まで受験可能でした。そうなったら別にどちらでもいいやとなって(笑)。それで学院を受験・合格し、入学することになった次第です。クラスにも、私と同じような高校浪人組や地方出身者など、1年遅れで入学した仲間が3~4人いました。
――入学後、学院での生活はどのようなものだったでしょうか?
私達の頃は、今と比べればハチャメチャでした(笑)。下町育ちのクラスメイトに麻雀を教わったんですが、習い始めだと楽しいわけです。そうすると、お昼のお弁当を食べたら仲間と「さあ行こう」となるんですが、ただ早退しただけでは(空席があるので)先生にすぐばれてしまう。そこで、4人分の机と椅子を廊下のロッカーの上に載せて隠し、何回かはやり過ごしました。ただ、しばらくして発覚し、とても怒られました(笑)。
担任は1年生の時が倫理の富永厚先生、2~3年生の時は数学の喜多見猛先生でした。富永先生は2023年までご健在でしたので、私達が50歳を過ぎた頃から、先生もお招きして何度かクラスの同窓会を開催しました。残念ながら物故者や音信不通の人もいますが、それでも30人ほどが集まりました。
とにかく、学院時代は勉強した記憶がほとんどない(笑)。私はギリギリで卒業したようなものだったと思います。学院そして学院生も、全体的にまだバンカラな雰囲気を色濃く残していました。

富永先生を囲んでの同窓会にて(2013年)
――今でもクラスメイトとの繋がりが続いているんですね。
当時大学で言われていたのが「学院出身者は本当に優秀な奴か、ダメな奴しかいない」ということでした。政経に進んだ優秀なクラスメイト2人は、卒業時に総代と2番目だったそうです。そういう風にきちんと勉強する人間と私のように遊んでばかりの人間が混じっていたわけですが、卒業すれば全員大学に進めるので、ギスギスしないところが学院の校風でしたね。彼らとも今でも交流が続いています。先生も大学のような感じで、赤点取ったら自己責任、かといってお尻を叩いてやらせるわけでなく、留年する生徒も普通にいました。
――そのような中で、当時から流派を継ぐことを決めていたのでしょうか?
私は3歳の時から父(十世 西川扇藏)に稽古を付けてもらっていました。そうすると、周りのお弟子さん達が「この子が将来は流派を継ぐんだ」という目で見ます。なので決めたというより、自分でも自然とそう思っていたところがありました。ただ、その後大学を卒業する時に母から「何かやりたいことがあればその道を選んでも構わないし、踊りを強制することはしない」と言われました。やるなら自分の意思に基づいて進んでほしい、やらされているという感覚では家元としてものにならない、ということだったんだと思います。それで、踊りの道に進むと自ら決めて現在に至ります。
とはいえ今振り返ると、学院時代は遊びたい盛りでしたから、稽古があって友達と一緒に行けない時など、ストレスを感じることもありました。ですから、そのような青春時代を共にした学院時代の同級生とは、付き合いの濃度が非常に高いと思います。先ほど話した麻雀仲間とも、今でもよく集まりますよ。
――日本舞踊の家元の子として、注目されることはありましたか?
みんな興味を持ってくれましたよ。私は学院の卒業式は紋付袴で出席することにしていたのですが、そうしたら成績は悪かったのにクラスの総代に選んでもらいました。ところが留年するかもしれないということで(笑)、担任の喜多見先生が一応代理を決めておこうと提案したところ、クラスメイトのひとりが「その必要はない。西川は絶対に大丈夫です」と言ってくれました。彼も成績優秀で政経に進んだ人だったのですが、勉強だけに囚われず、互いの個性を認め合う仲間意識が学院にはあったと思います。

2021年に日本芸術院賞を受賞した際、クラスメイトから贈られた人形
――お友達との思い出の他に、何か印象に残っている出来事はありますか?
学院2年の時に、ラグビー部が花園出場を果たしました。現TBSホールディングス社長の佐々木卓さんが主将だったことを覚えています。國學院久我山高校と対戦した東京予選の決勝を自宅でテレビ観戦しました。強豪相手に終始押されながらも僅差で勝利し、感激しましたね。当時の学院そして早稲田大学といえば、ラグビーがシンボリックな存在だったと思います。もちろん野球の応援にも行きました。昨年、学生時代以来約40年ぶりでしたが、家族と早慶戦を観に行きましたよ。
――最近は硬式野球部が強くなり、学院出身の選手が六大学リーグ戦にも多数出場しています。
そうですか。それでは(昨夏の甲子園で優勝した)慶應義塾高校のような夢を我々も見たいですね。
――学院卒業後は第一文学部文学科の演劇専修(当時)に進まれました。
早稲田といえば河竹繁俊先生に始まる演劇学の伝統があり、名前こそ演劇専修でしたが、私の在学当時から放送専攻を希望する学生の方が多かったです。今は映像演劇コースという名前だそうですが、放送・映像の分野がより表に出てくるようになりましたね。
演劇研究の対象には、能・狂言・文楽・歌舞伎といった伝統芸能から現代劇まで幅広く含まれます。その中で早稲田の伝統は、実技ではなく座学、すなわち研究・評論・歴史を学ぶということにあります。例えば現在私も教えている日本大学藝術学部では実技指導をしますし、サークル活動でも慶應の歌舞伎研究会は学生歌舞伎を上演する一方、早稲田は基本的に観劇専門です。
当時は郡司正勝先生という歌舞伎研究の大家がいらっしゃって、私の卒業と同時に退官されました。卒業論文の指導をして頂いたのですが、その時に助手として古井戸秀夫先生(東京大学名誉教授)がおり、資料の探し方などを詳しく教えてくださったのは古井戸先生でした。卒業論文では、父に至るまでの西川家の歴史について書きました。
――自らの家がテーマではあるものの、江戸文化の本質にも通じる内容になりそうですね。
歌舞伎や日本舞踊が発達した文化・文政時代は、町人による江戸文化の爛熟期でした。何か新事実を発見したわけではありませんが、家や芸事について、これまで認識していなかった事柄に気付かされることは多々ありました。自らのルーツを知るという意味で、やってよかったと思っています。

長唄「義朝朝長」にて、長女の佳さん(文化構想学部在学中)と共演
(2023年10月1日 国立劇場小劇場)
――大学を卒業後、イギリスへの留学も経験されました。
よく「芸に学歴は要らない」などと言いますが、私の母は教育熱心な人でした。伝統芸能の世界というのは狭い社会なわけですが、そうした狭い社会の中だけで生きていく人間にはなってもらいたくないと思ったようです。「これからは世界を相手にする時代になるんだから、どこかに留学しなさい」と言われて、留学をさせられたという恰好でした。でも、色々な経験ができて良かったです。結果的に2年半ほど過ごしました。1年目はほとんど英語の勉強で、その後Laban Centreというダンスの大学(現Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance)に入り、ダンスを学びました。バレエやコンテンポラリー・ダンスなど、全く異なる分野にも挑戦しましたよ。
ちょうど平成になった年に帰ってきました。昭和天皇崩御の際、The Timesの1面に“The Emperor Dies”という見出しが出たのをよく覚えています。日本のニュースが1面に載るということは、ほとんどありませんでしたから。そんな時代でした。
――周囲から見れば、西川さんは「演劇界のサラブレッド」だったのではないでしょうか?
確かに日本舞踊の家元に生まれましたが、学院の自由な空気の中で互いの個性を認め合った経験から、そのような見方とも自然に付き合うことができたのではないかと思います。そういう意味でも、私には早稲田の水が合っていたんでしょうね。あの頃から、変わっている人間はいくらでもいましたよ(笑)。
2024年3月9日 西川流稽古場にて
聞き手:33期 山口真一、63期 松村健太郎